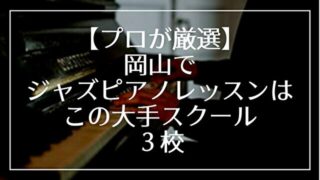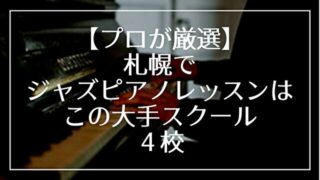レッスンでは「シマンドル」でなく「HIYAMAノート」の方を使っています。
なぜそうしているのか、少し書いていきます。
ちなみにHIYAMAノートは、シマンドルの「第一部」を抜粋して作られています。
ジャズ系ベーシストにとっては、一応この第一部だけで、必要最低限のテクニックは習得できます。
HIYAMAノート良いところ

HIYAMAノートの説明に確か、「シマンドルに、さらに必要な練習を追加した」のようなことが書いてあったと思います。
この「追加された部分」が、かなり有用で使っています。
フォームの練習
各章、頭の部分に左手のフォームの練習が載っています。
シマンドルには載っていない練習です。
リピートマークだらけの部分ですね。
指を開くシマンドルスタイルのフォームを覚えること、それに加え、音程の確認に、この部分は有用です。
インターバルの練習
「2度」とか「3度」などとなっている部分がありますね。
このインターバルの練習は、とても効果的です。
単純に弾くのが難しいですが、それに加え、音と音の距離に敏感になることが、たとえばジャズを演奏する場合など、重要なスキルになってきます。
ちなみに「3度」の部分の練習は、ぼくが勝手に「くねくね練習」と呼んでいるものと同じです。
»「くねくね練習」は、どのスケールにも有効【ジャズの基礎練習】
分散和音の練習
コントラバス(ウッドベース)で分散和音を弾くことはとても難しいです。
ピアノやギターだと簡単なのに、コントラバスだと、こんなにも難しくなるのか、といった感じですね。
ポジションの選び方によっては移動距離・回数が多くなり、音程の問題がさらに追加されます。
ぜひこの分散和音の部分を活用しましょう。
あのスコット・ラファロも、分散和音をたくさん練習したようですよ。
弦を変えた練習
本家のシマンドルの方に載っている練習の、キーを変えて他の弦で練習させている部分があります。
ここも良い練習になります。
苦手なひとが多い、2~4弦の中域~高域が、自然に把握できるようになります。
価格が安い
あと、ちょっとだけ嬉しいことですが、本家シマンドルより値段が安いです。
安いに越したことはないですね。
HIYAMAノートのリンクを載せておきます。
できればシマンドルも持つと良い

以上、HIYAMAノートを使う理由・メリットを書いてみました。
ただシマンドルの第二部も良いメロディが載っているので、本当はシマンドルも持っておいて欲しいとは思っています。
難易度的に、次に取り組む「30エチュード」への橋渡しになるので、30エチュードが難しいと感じる場合には、第二部も練習してみてください。
ちなみにシマンドルはこの本です。
それでは以上です。
このページは、
シマンドル/HIYAMAノートのブログ記事まとめ【コントラバス】
追加しました。